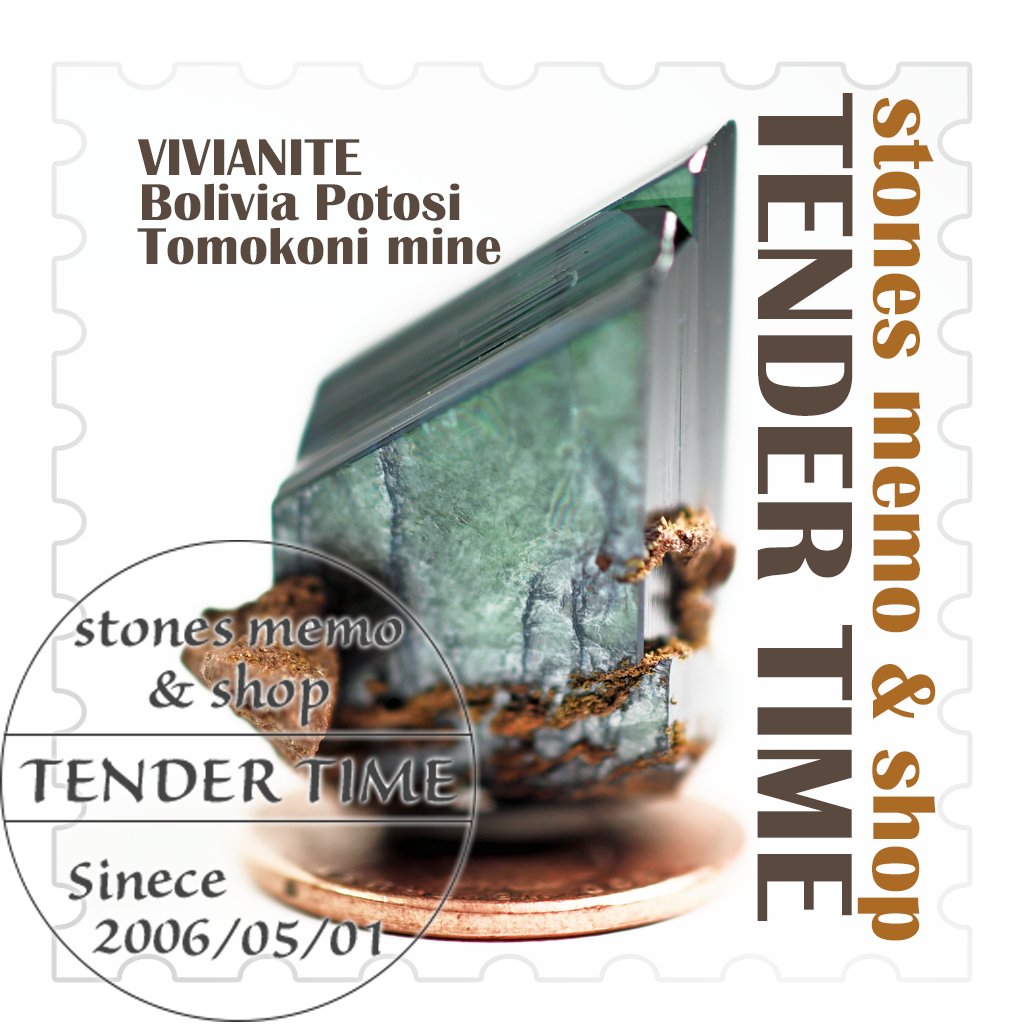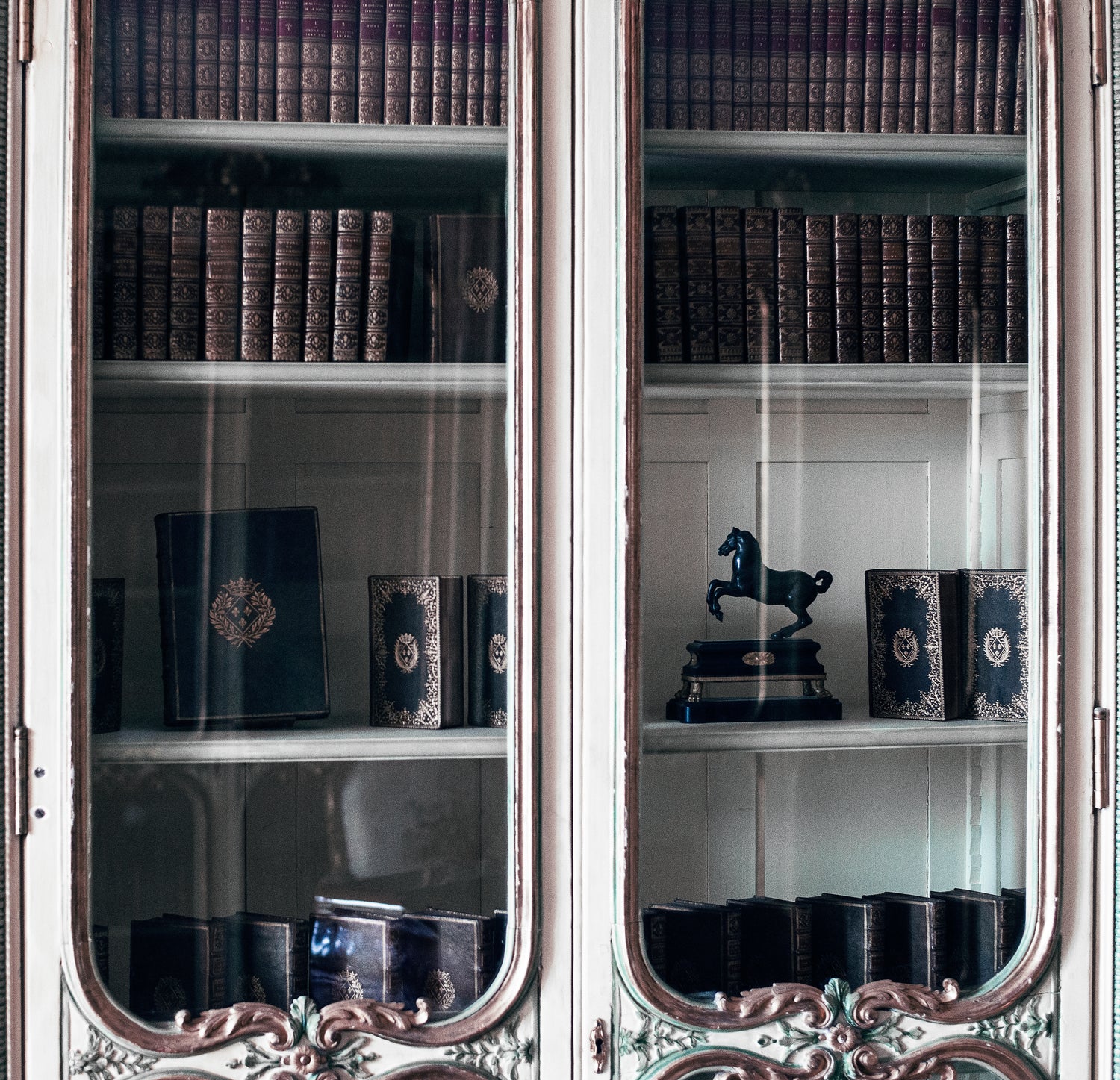珪化木 和賀仙人鉱山
Petrified は化石・石化という意味で、木の化石のこと。
あちこち見てみると、Silicifide WoodやSiliconization Wood -シリカが染み込んで石化した木-や、もともとの木の種類のAraucaria -ナンヨウスギ-等を書いたものといろいろ見かけました。
一番馴染み深いのはPetrified woodかと思います。
化石への道

珪化木 和賀仙人鉱山
化石は木の化石もありますし、生物・植物などいろいろあります。
化石になるまでを簡単に記します。
1.埋まる
化石となるには分解されずその形を残さなければ化石となりえません。
死が訪れた後、分解されずに残るには、早くに埋まらなければいけません。
海や湖の中等の水中は陸上よりも早く埋まります。
陸上の場合は洪水などで一気に流され川の底に埋もれた場合や、火山灰に埋もれた場合などが考えられますね。
2.鉱化
埋もれた素材の柔らかい部分が分解され、その分解された空間に鉱物になるような物質が溶け込んでいる水が染みこんで沈着し、鉱物化していきます。
珪化木の場合は、ケイ素が地下水の中に溶けていて、シリカ(二酸化ケイ素)に置換という経過をたどります。
3.固まる
堆積物が次から次へ重なってどんどん埋もれていくと、その重みで圧縮されて固化していきます。
4.発見
埋もれたままでは化石は目に触れません。
地層の隆起や侵食等が起こり、地表に出て発見となります。
ウッドオパール

上記イラストにて説明した”珪化木ができるまで”と同じ生成過程を経てオパール化したものをウッドオパールといいます。
珪化とオパール化と瑪瑙化
| 珪化 | ケイ酸を含んだ水がしみ込み、固くなる。または、生物(植物含む)の亡骸に同じくケイ酸を含んだ水が染みこみ固くなる→化石化する。 |
| オパール化 | 同じくケイ酸を含んだ水がしみ込んだけれど、水分を含んだままで結晶していないもの。鉱物=結晶していることという鉱物の定義からは外れているけれど、宝石としての人気は誰もが知るところ。 |
| 瑪瑙化 | 一つ一つの結晶がとても小さく存在するため、見た目は半透明の塊に見える。 |
と、なんとなく頭のなかで分けていました。
今回少し調べてみたのですが、シリカ(二酸化ケイ素)は結晶性と非結晶性の2種類があります。
実際のところ、瑪瑙のスライスの真ん中に小さな結晶を見かけることも多々ありますし、また、瑪瑙も結晶性と非結晶性が厳密には混じって存在することもあるとの記述がありました。
そして、シリカが沈殿した際の成長の進み具合として、時間の経過もしくは温度上昇があると脱水と結晶化が進み玉髄質石英(瑪瑙化)となって安定するとのこと。
天然石と言われた時に一番身近な”水晶”、つまり石英ですが、この石英は二酸化ケイ素の結晶です。
そしてその姿の多様さにいつもしてやられます。
ケイ素と水
元素記号 14 Si ケイ素
英語名はシリコン
地殻はケイ酸塩鉱物がメインです。
ケイ酸塩鉱物は、全鉱物の40%を占め月・隕石の主要な構成成分です。
そんな中を地下水が行き来しているので、結果的に水にケイ素が混じっている事がほとんどです。
温度が高くなればなるほど水にケイ素が溶ける割合は高い※1ため、温度の高い地下の深い場所でたくさんのケイ素を取り込みます。
その水が地表近くまで来た時、温度が低くなることにより地表から比較的浅い場所でケイ素を沈殿させることになり、私達の目を楽しませてくれています。
※1 300度以下の場合
基礎データ
| 化学組成 | 珪酸塩鉱物 SiO2 |
| 色 | 褐色・灰色・ピンク色・赤色・紫色・黄色等 バリエーション豊かでそれぞれ独特の絵がみられます。 |
| 条痕 | 白色 |
| 結晶系 | 六方晶系 |
| へき開 | なし |
| 硬度 | 7 |
| 比重 | 2.7 |
産出地 産状

米アリゾナ州 Petrified Forest National Park -化石の森国立公園-が不動のNo.1で有名です。
WEBサイト Petrified Forest
グーグルの地図の紹介写真でも、公式サイトでも見れますが、高地砂漠の荒涼とした風景の中、ゴロンと横たわる木があちこちに見えます。
この化石の森国立公園は、三畳紀(今から約2億5100万年前~1億9960万年前)の木の化石で、三畳紀当時は、パンゲア大陸の縁辺部に位置する盆地で、とても背が高く幹周りも何メートルもあるような針葉樹の森だったとのことです。

珪化木 和賀仙人鉱山