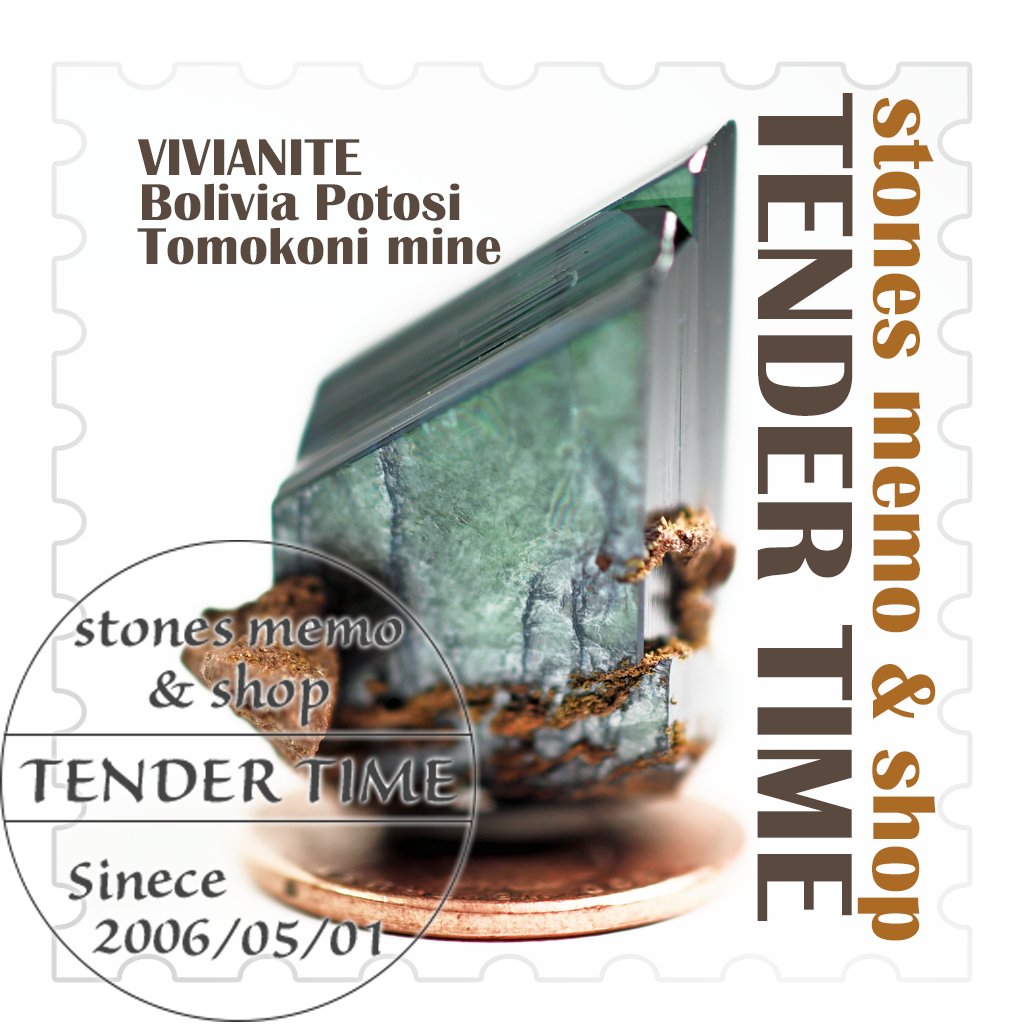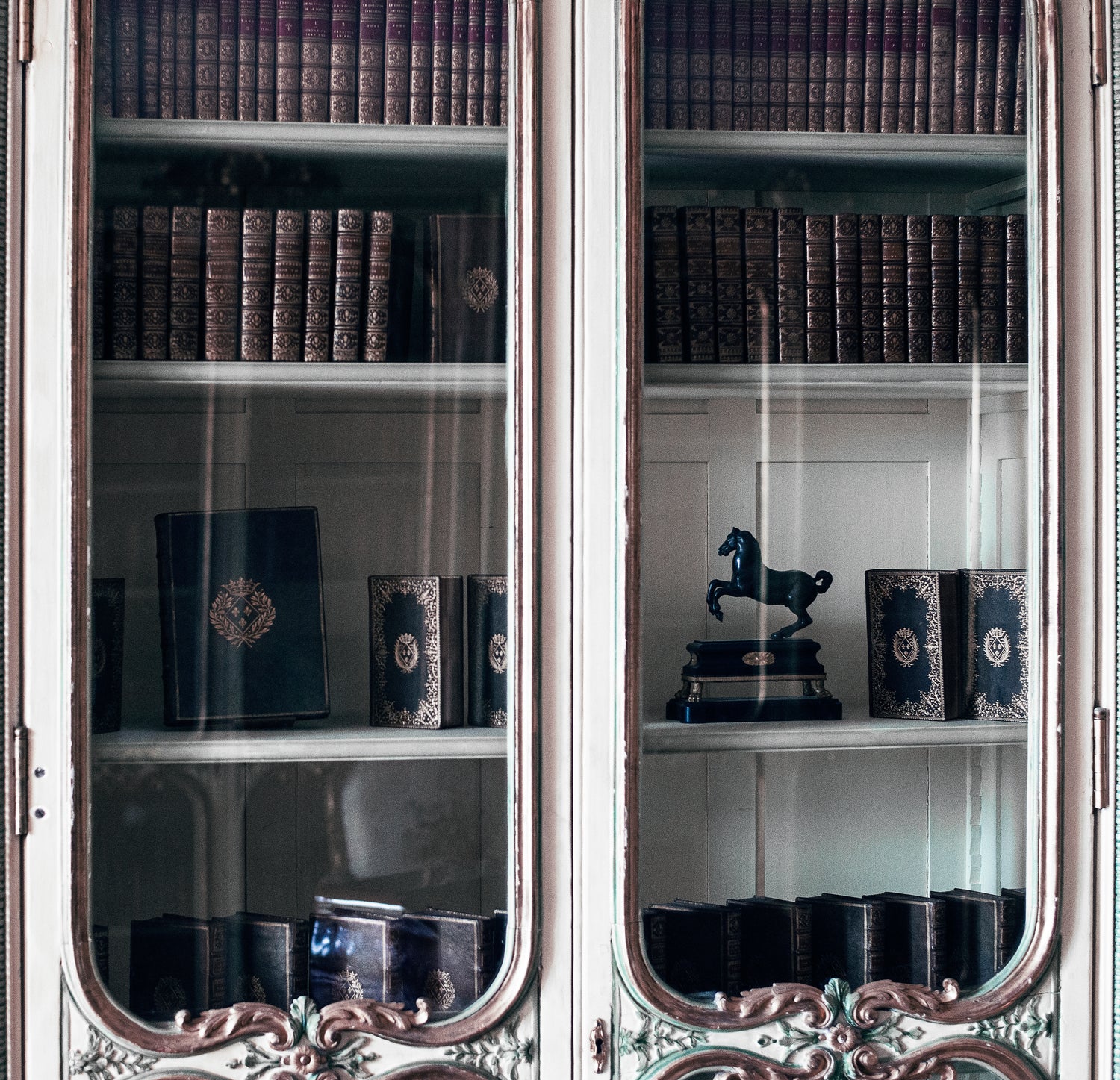デモストラトゥスは琉拍をリュンクリウム<リュンクスの小便>と呼びそれはリュンクス<オオヤマネコ>として知られている野獣の小便からできたもので、雄は黄褐色で燃えるような色のものを、雌はもっと薄くて明るい色のものをつくるのだ、と主張している。 彼にしたがうと、琉拍をラングリウムと呼び、イタリアに住んでいる獣はラングリであると言っている人もあるという。
ゼノテミスはその同じ動物をランゲスと呼び、それはパドウス河の岸にいるという。
一方スディネスはリグリアにある琥珀をつくり出す木はリュンクスと呼ばれると書いている。
メトロドロスも同じ意見である。
琥珀は動物のおしっこからできている。
このことについてたくさんの人の話をプリニウスさんは紹介しています。
それぞれのお話を聞いてみましょう。
デモストラトゥスさん曰く
琥珀はリュンクリウム<リュンクスの小便>と呼ばれているんだ。
リュンクスとはオオヤマネコのことで、オスのおしっこからは黄褐色で燃えるような色でメスのおしっこは薄くて明るい色なんだよ。
でもね、このリュンクス<オオヤマネコ>のことをイタリアに住んでいる獣はラングリっていう名前で、琥珀はラングリウムっていう人もいるんだよね。
ゼノテミスさん曰く
このリュンクス=ラングリ=オオヤマネコはランゲスっていう名前だよ。
パドゥス河=ポー河の岸にいるよ。
スディネスさん曰く
リュンクスってさぁ、リグリアにある琥珀を作る木の名前なんじゃないの?
メトロドロスさん曰く
あ~それ、おれもそう聞いたよ。
という展開です。
伝達ゲームの成れの果てというか言い伝えってこういう風に展開されていくのよねきっと的な感があります。
上記記載の文章をちょっと飛ばして、もっと後のほうに、”リュンクリウム”という段落が存在します。
リュンクリウム
次にわたしがリュンクリウムについて語らざるを得ないのは、わが国の権威者たちの頑固さのためである。
というのは彼らはこのリュンクリウムが琥珀であると断言することを差控えるときでも、彼らはこれは一種の宝石だと主張し、それはほんとうはオオヤマネコの小便からできるのだが、また一種特殊な土からもできると述べているからである。
プリニウスさんの反撃が始まります。
彼らはこの動物は人類に対して一種の怨恨を抱いており、直ちに自分の小便を隠すのだが、それがそこで石になるのだと言っている。
この石は琥珀と同じく焔色をしており、彫刻することもでき、また枯葉や藁だけでなく、銅や鉄の削り屑をも吸引するという。
怨恨…恨んでいるから自分のおしっこを隠す…なぜ?^^;
吸引という部分ですが、琥珀は摩擦すると静電気を発生させますが、このことが言われているのではないでしょうか?
この信念は、あるディオクレスという人の言を典拠として、テオフラストス※1さえ受け入れている。
※1テオプラストス(wikiより引用)
(希: Θεόφραστος, Theophrastos, 英: Theophrastus、紀元前371年 – 紀元前287年)は古代ギリシアのレスボス島生まれの哲学者、博物学者、植物学者である。植物研究における先駆的な功績から「植物学の祖」と呼ばれる。アリストテレスの同僚、友人で、逍遙学派の主要人物の一人であった。
わたし自身(プリニウス自身)の意見では、こんな話は全部嘘で、そんな名をもった宝石には、現代においてお目にかかれないのだ。
また同時に、その医薬的性質について述べられていること、すなわち、それを液に入れて飲むと膀胱結石が砕けるとか、それをブドウ酒に入れて飲むか、あるいはそれを見るだけでも黄だんが癒えるなどということも嘘である。
この文章の前に医薬的な部分に触れている文章があるのですが、プリニウスさんはその内容をカリストラトスさんの話として紹介しています。
嬰児に護符としてそれをつけておくと御利益がある。
カリストラトゥスは言っている。
年齢を問わず、激しい精神錯乱の発作や排尿困難の治療剤としても有効であり、どちらも液に入れて飲むか護符として身につけると。
この時代ですから、まずお守りから入っていますね。
そして、おしっこから離れられない!
ちなみに現在、漢方薬で琥珀が使われてるそうで、安眠・イライラに良いと言われています。
また、いわゆるコハク酸はうまみ成分として調味料に入ってますね。
この著述家はまた一種の琥珀にクリュセレクトルム<黄金琥珀>という名を与えて、新しい栄誉を導き入れた。
それは黄金色で朝のうちはいたって美しい外観を呈しているが、たいへん引火しやすく、焔に近づけるとその途端に燃え上る。
カリストラトゥスによると、この種類の琥珀は、首飾りにつけて護符として身につけていると、発熱や病気を癒し、粉末にしたものをハチ蜜およびバラ油に混ぜたものは耳の病気を、また粉末をアッティカハチ蜜と混合したものは弱視を、細かい粉末をそれだけ、または乳香といっしょに水に入れて飲むと、胃の病気すら癒すという。
黄金琥珀の件ですが…
特別な種類とネーミングを付けて、これはこれに特別に効くんですよ…だもんで、普通の琥珀よりもお値段が…(パチパチパチ)…こんなんでどうでしょう?という現在でもよく聞くこのパターンと思われます。
琥珀に纏わる話は続きます。
ソタクスは、琥珀はブリタニアにあるエレクトリデスという岩壁から流れて来るのだと信じている。
ピュテアスは大洋にメトゥオニスと呼ぱれ奥行が七五〇マイルもある入江があって、その岸にはゲルマニア人の一種族グイオネスが住んでいると語っている。
ここからアバルス島までは一日航海の距離であって、春になるとこの島へ琥珀が海流によって運ばれて来るが、それは固体化した塩水からなる一種の排池物である、と彼は言っている。
彼はつけ加えて言う。
その地域の住民は、それを木の代りに燃料として用い、それを近隣のテウトン人に売る、と。
彼の信念はティマイオスにも分け持たれているが、ただティマイオスはその島をバシリアと呼んでいる。
岩壁から流れて来る
琥珀は針葉樹など木の樹脂が化石化してできますが、岩壁という部分は、その昔にたくさんの木に覆われた大地が地殻変動によってぽこんと出てきた岩壁と考えると、琥珀の産状として想像がつくと思います。
通常の琥珀の比重は約1.05~1.09とのこと。
海水の比重は1.01~1.03程。
海水の中に琥珀があった場合、水中を漂います。
春になるとこの島へ琥珀が海流によって運ばれて来る
地殻変動によって海中及び海岸の岩壁などから海の中を旅して、海流の関係である季節に集中してその島に流れ着くということも想像がつきます。
固体化した塩水からなる一種の排池物
これは、マッコウクジラの龍涎香(りゅうぜんこう/ambergris)といわれる香料が浮かびます。
これは、マッコウクジラのう〇ちともいえる排泄物。
マッコウクジラのご飯であるイカなどのくちばし部分の固いところが消化しきれず、おなかの中で結石となり排泄されたもの。
色味は琥珀と同じ色合いのものだけでなく、蝋状で白や黄色・緑色などもあります。
琥珀と見た目が似ているためにその昔はこれと琥珀は同じものと言われていました。
参考 wiki龍涎香
木の代りに燃料として用い
ヨーロッパでは、琥珀を暖炉に投げ入れて燃やして香りを楽しむということがあります。
ブリタニアとは、グレートブリテン、つまりイギリス、グレートブリテン島の南部をさします。
現状調べた限りではイギリス南部はかなり古い時代の原産の琥珀(白亜紀)と、バルト海から流れ着いた琥珀があるとのことでした。
そして有名人が登場しています。
ピュテアス(wikiより引用) (古希: Πυθέας ὁ Μασσαλιώτης、紀元前4世紀)は、ギリシア植民都市マッシリア(現在のマルセイユ)出身のギリシア人地理学者、探検家。 紀元前325年ごろ、北西ヨーロッパへの冒険航海に出た。 グレートブリテン島各地を訪れている。
この方、この時代に実際に行っている方です。
ですが、この方自身の探検記は残っておらず、このプリニウスさんの博物誌が、この方の記録の手掛かりとして重要視されています。
プリニウスさんだけでなくほかの方もその記録を残しているのですが…
リンク先にありますが、今も昔も変わらない人間臭さが存在しています。
ご興味があればリンク先(ピュテアス-ブリテン諸島発見)を読んでみてください。
プリニウスの博物誌 琥珀1にて、琥珀にまつわるギリシア神話としてパエトンの話を紹介しましたが、また一つご紹介します。
メレアグロスはカリュドンの地を治めるカリュドン王オイネウスとその王妃アルタイアの息子。
メレアグロスが生まれたとき、3人の女神があらわれ”子供の命は炉に燃えているその燃えさしほどももたない”と予言された。
驚いた母アルタイアはその燃えさしをとって火を消し、大切に保管した。
そして時は流れメレアグロスは大きくなった。
そんなある日、オイネウスが神々に生贄を捧げていたが、女神アルテミスだけ省いてしまった。
のけ者にされたと思って怒り狂ったアルテミスはカリュドンの地に大きな野猪を放った。
その野猪のおかげで穀物や葡萄やオリーブなどの食料はもちろん、小鳥や獣の群れまでもめちゃくちゃにされてしまい荒れ放題となった。 オイネウスはギリシアの英雄を集め、猪狩りを実行した。
メレアグロスはもちろん参加し、英雄たちが猪狩りに集った。
その中で女性が一人だけ参加した。
アルカディア王の娘アタランテ。
美しいアタランテにメレアグロスは恋をした。
猪狩りが始まり、集った仲間たちがそれぞれ戦った。
その中で小さいながらも最初に猪に傷を負わせたのは女性であるアタランテであった。
そして猪に致命傷を与えたのはメレアグロスだった。
狩りが終わると皆集まってきた。
メレアグロスはアタランテに戦利品として野猪の毛皮をおくった。
すると嫉妬から、メレアグロスの母アルタイアの弟たちがアタランテから毛皮を奪い取った。
メレアグロスは恋心が勝りアタランタを侮辱したと弟たちを怒り、身内であるにもかかわらず狼藉者として殺害してしまう。
アルタイアは事の成り行きを知り、母である自分と姉である自分との間で心は揺れに揺れた。
”メレアグロスは生きてこの先このカリュドンの地を治めるべきではない。
そうあってはならない。
なぜなら私の弟たちは復讐もできず幽霊のようにさまよわなければならない。
メレアグロスは死なねばならない。
私が殺さなくともメレアグロスは死なねばならない。
私は2度、メレアグロスに命を与えた。
一度目はあなたを生んだ。
二度目はこの燃えさしを奪い取った。
弟たちよ、あなたたちの勝ちです。”
アルタイアは顔を背けながら燃えさしを炎に投げた。
別の場所にいたメレアグロスは突然苦しくなり、なぜか体が燃え出した。
苦しさの中でなぜこんなことになっているのかわからないメレアグロスは、父や母の名前を呼んだ。
燃えさしの炎が消えると、メレアグロスの命も消えた。 その後、アルタイアは自殺した。
メレアグロスの姉妹たちは兄の死を悲しみ、泣き暮らした。
ただただ泣いて泣いて泣いた。
野猪を仕向けた女神アルテミスは自分を怒らせたその家の不幸を憐れんで、姉妹たちをホロホロチョウに変えた。
それでも泣いて泣いて泣いた。
その流した涙は琥珀となり、岸辺にたどり着いた。
補足
女神アルテミスの生贄は、省いたのではなく忘れちゃったと書かれているもののほうが多かったりします。
ギリシア神話も日本昔話も微妙にところどころ違う展開や違う結末になっているものがありますので、もちろんお分かりだと思いますがご了承ください。
そしてこの神話に絡めて続きます。
だが、これらすべての著述家たちを凌いだものは、悲劇詩人ソフォクレスである。
これらすべての著述家たちとは、今まで数々の琥珀に関する人から聞いたお話をプリニウスさんは紹介してきましたが、その話の語り部たちのことです。
ソフォクレス(wikiより引用)
(ギリシャ語: Σοφοκλῆς, Sophoklēs, ギリシア語発音: [so.pʰo.klɛ̂ːs]; 紀元前497/6年ごろ – 406/5年ごろの冬[1])は、現代まで作品が伝わる古代ギリシアの三大悲劇詩人の一人。ソポクレースは生涯で120編の戯曲を制作したが、そのうち完全な形で残っているものは7作品にすぎない。
ソフォクレスさんは今に名を遺す三大悲劇詩人のひとり。
有名な作品はオイディプス王。
プリニウスさんの話を続けます。
そしてこのことは、彼の悲劇が非常に厳粛なものであり、そのうえ、彼がアテナイの貴族の家柄の出であること、彼の公人としての功績、軍隊の統率力などによって、その個人的名声が一般にきわめて高いことを考えると、少なからずわたしを驚かすのである。
ソフォクレスは、琥珀はインドの向うにある国々でメレアグリデスの娘たちとして知られている鳥が、メレアグロスのために流す涙からできるのだと言っている。
彼がこんなことを信じ、他の人々にもそれを受入れるよう納得させることを望んだというのは驚きではあるまいか。
いぶかしいことだが、毎年泣いたり、そんなに大きな涙をこぼしたり、メレアグロスを悼むために、彼が死んだギリシアから、インドへ渡って行った鳥があった、などということを真に受けるくらい幼稚でうぶな精神を想像し得るだろうか。
簡単にすると…
ソフォクレスはとても立派な人物だということは誰もが知るところだ。
そんな彼が、琥珀はメレアグロスのために流す涙でできていると言っている…
それをソフォクレスは信じていて、ほかの人にも信じるように納得させようなんてありえな過ぎて驚きだよ!
そもそも、毎年泣いたり、涙の粒が琥珀ほどに大きいだって?
メレアグロスを悼むため、死んだ場所のギリシアからインドへ渡った鳥を真に受けるなんてまるで子供のようじゃないか!
評判の彼の精神がそんな子供のようだなんて想像できないよ。
毎年泣いたり
琥珀は海流の関係で季節的に岸に流れ着くことを知っているので、毎年定期的に泣くという解釈の上の発言と思います。
インドの向うにある国々でメレアグリデスの娘たちとして知られている鳥と死んだ場所のギリシアからインドへ渡った鳥
翻訳の問題もあると思いますが、少し言い回しが変わっています。
ソフォクレスさんはインドの向うにある国々でメレアグリデスの娘たちとして知られている鳥と言っています。
プリニウスさんはギリシアからインドに渡っていった鳥と表現しています。
プリニウスさん自身この神話の中のホロホロ鳥はギリシアからインドへ渡った鳥という情報がありその認識があったとも考えられますが、ソフォクレスさんの主張を受けて論破しようとちょっとオーバーに発展させて、つい口走ってしまった感を禁じえません…
もっとプリニウスさんを知りだすとまた違う解釈をするかもしれません。
それぞれのプリニウスさんの面影を重ねて考えみるのもまた一興です。
ちなみに、ホロホロチョウはアフリカで生息しており寒さが苦手、ちょっと神経質だけどめちゃめちゃ丈夫で薬いらずとのこと。

Derek Keats from Johannesburg, South Africa, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons, original data
[[ホロホロチョウ つがいと雛]]
してみると、これら詩人たちによって語られたもので、同じように根も葉もない話がほかにもたくさんあるのではあるまいか。
その通り。
だが誰であろうとも、このような物質、日常日々輸入されて市場に溢れ、そんな嘘をぬり込めている物質について、真顔でこんな話をするなどとは、人間の知性に対するゆゆしい侮辱であり、偽りごとを言ってもよいという自由の、許し難い乱用である。
メレアグロスの神話は、ホロホロチョウと明記されていない文献も存在します。
単なる”鳥”という表現であったり、メレアグロスの神話の最後に琥珀のこの字も出てこない、鳥に変えたという終わりだけのものもあります。
正直なところ、このメレアグロスの話もパエトンの話も琥珀を後付けした感じがしなくもない…
というか、だよねきっと…と思ってしまってる私がいます。
そして美しく、これはいったい何かということもはっきりしていない、男性のにとって永遠の謎である貴婦人たちにとても人気のもの。
そんなものを伝説の中で語りその価値をさらに高めたと考えれば、今も昔も変わらない、人間の心理がそこにあると思います。
プリニウスさんの琥珀に関し伝説級の話が多く、プリニウスさん本人もうーん?と思いつつ聞いた話をそのまま紹介し、資料として博物誌に残しています。
聞いた話に対するプリニウスさんの見解の言葉はだいーぶキツめですが、私の中のプリニウスさんはそこまで無粋な人じゃないと思っています。
伝説やいわれは人の文化の中にあって当然なもの。
時に人の心に働きかけて神話などを語ることにより、そこから学ぶ教訓的なものは教育にもつながりますし、時にいわれを流布して商売につなげるという生活の質に反映することもあると思います。
そう考えると、それはそれ、これはこれときちんと住み分けたうえで判断をしようとしていると感じます。
ただ、今も昔も変わらないきちんとした線引き=これは何?という真実といわれ的なものをごちゃまぜの状態はよろしくないと感じている一人なのではと思っています。
なぜならば、先ほど話したように人の文化に反映される大切なことだから。
ーーー
出典 プリニウスの博物誌(全3巻). (1986). 日本: 雄山閣.
プリニウス(23~79年→古代ローマ時代)が書いた”博物誌”
天文・地文・気象・地理・人種・人類とその発明・動物・植物・農業・造林・金属・絵画と顔料・岩石・宝石など生活に結びついたあらゆる分野を取り扱い、人類初の百科事典と言われます。
この中で、第33巻(金属の性質)・第34巻(銅)・第36巻(石の性質)・第37巻(宝石)が鉱物関連の記述です。
ここに書かれている石の話です。