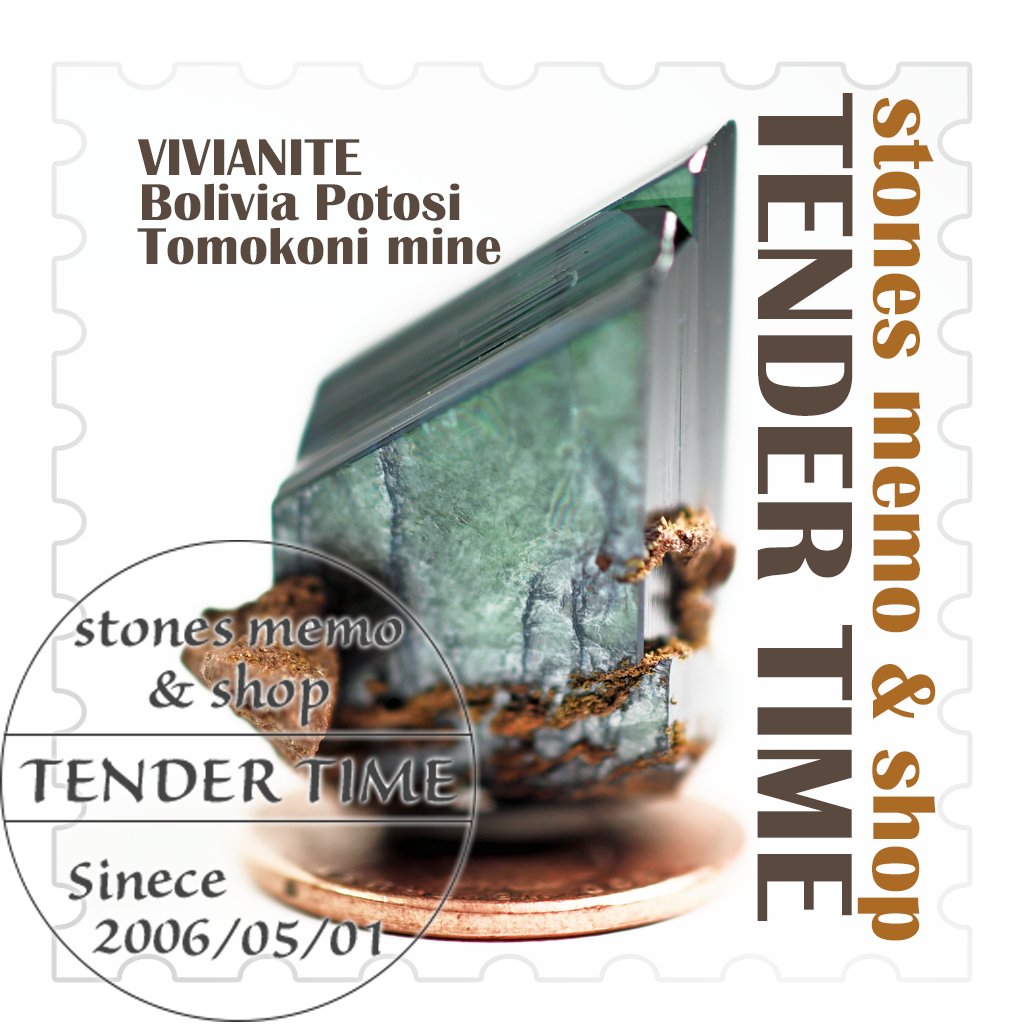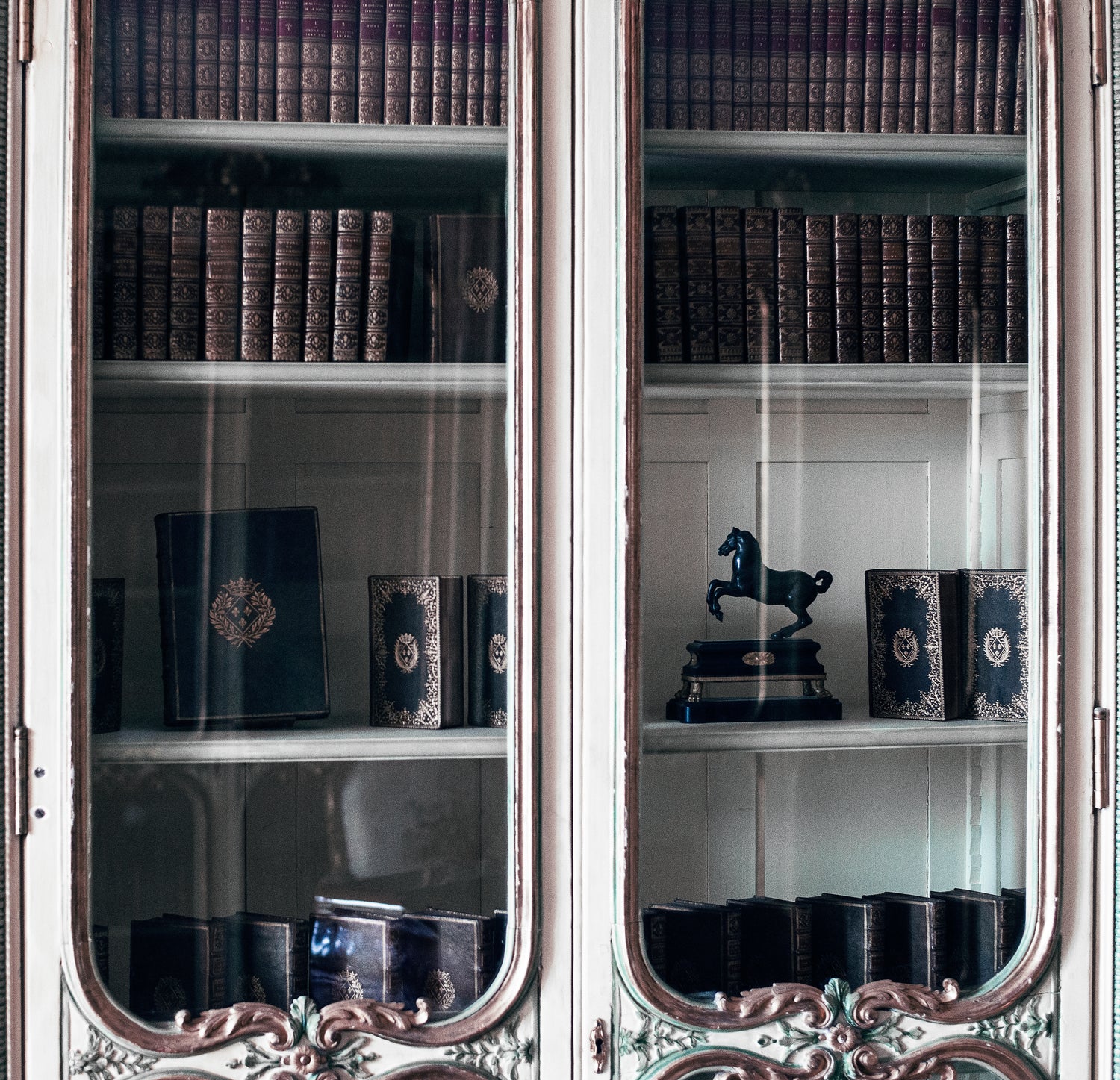ベリル(beryl・緑柱石)とは、有名どころの石をたくさん兄弟に持つ石で、アクアマリン・エメラルド・ゴシェナイト・ヘリオドール・モルガナイト・レッドベリルなどがあります。
その ベリル を プリニウスの博物誌 で取り上げています。
エメラルド
エメラルドは”プリニウスの博物誌”の中で、”スマラグドゥス(緑玉)”と言われています。
しかし、この”スマラグドゥス(緑玉)”とは、エメラルドを含む緑色の石全般を指す言葉。
プリニウスは”十二種類のスマラグドゥスがある。”と述べています。
トップ3は…
1 スキタイ種
どの種類もこれ以上に色が深く、これ以上に無瑕(※傷のないこと<むか>)のものはない。
スキタイとは遊牧騎馬民族国家で、現在の南ウクライナの辺りです。
ベリルが切手の絵柄にもなっている国です。
2 バクトリア種
砂漠に風が吹く時に、住民が岩の割れ目から拾って集める。
3 エジプト種
エジプトのテーベ地方の市コプトスの近くで小山にある鉱山から採掘される。
古代エジプト時代に上エジプトで営まれた地方都市の名前で、現在のルクソールの北方にあたります。
その他の種類は、銅鉱山から産出される。
それらのうちで第一位を占めるのはキプロス産の石である。
これは、孔雀石と考えられているそうです。
以上のことからも緑色の石=エメラルド=スマラグドゥス(緑玉)ではないことがわかります。
更に、
スキタイやエジプト産のものはひじょうに硬くて叩いても割れない。
との記載も見られます。
同じ石で性質が著しく違うというのは、考えにくいことですね。
他にも色々書いてありますが、現在ではこの名前の石はこの石だという断定はできません。
その昔、見た目で分類することが主流だった時代の石の評価は、現在から見ると紛らわしくもあり微笑ましいものでもあると思います。
そしてこの緑柱石の最初の文章。
多くの人々は緑柱石の性質はスマラグドゥス(緑玉)と、同一でないまでも、似ていると考えている。
感づいていたんですね(笑)
”スマラグドゥス(緑玉)”はエメラルド。
エメラルドは緑柱石(ベリル)の仲間。
別項目ということが今となっては不思議ですよね。
そして続きます。
緑柱石はインドで生産され、他の場所では殆ど見られない。
それらはすべて熟練した職人の手によって、滑らかな六角形に彫摩される。
というのは、その色は、最初は彫摩されていない表面が濁って死んでいるが、彫摩すると表面からの反射によって価値が高められるから。
それをその他のどんな方法で彫摩しても輝きは出ない。
当時はインドで産すると考えられていて、インドの職人によってきれいな形に整えられていたのですね。
もともと柱状の六角形の形で産することが多い緑柱石ですが、更に磨きをかけてピカピカにしていたのですね。
一番貴ばれる緑柱石は、純粋な海の緑を再現されるものであり、それについで価値があるのはいわゆる”金緑石”である。
金緑石とは、よく知られているのがこの金緑石の変種であるアレキサンドライトやキャツアイなどがあります。
この金緑石は緑柱石と非常に似ている物があります。
プリニウスさんのお話の中では、緑柱石の分類の中に金緑石が組み込まれています。
そして順に、
クリュソプラスス(緑玉髄)
ヒュアキンティゾンテス(サファイア色緑柱石)
アエロンデス(空の青)種
ロウ色の緑柱石 油色緑柱石(オリーブオイルの色)
水晶に似たもの
と、プリニウスさんはおっしゃっています。
アエロンデス(空の青)種がアクアマリン?
油色緑柱石(オリーブオイルの色)はヘリオドール?
水晶に似たものはゴッシェナイト? と思いたくなりますが、遠い遠い昔のこと。
一体どんな石をプリニウスさんは見ていたのでしょう。
なんだか分類だらけの話になってしまいました。
最後に、プリニウスさんの素敵な石の文章を少しだけ記載したいと思います。
スマラグドゥス(緑玉)の項目より
我々は稚い植物や葉をじっと見つめるけれども、それよりはるかに大きい喜びをもってスマラグドゥス(緑玉)を見る。
比べてみると、それ以上に濃い緑色をしているものはほかにないからである。
~中略~
実際、他のものを見て視力を乱用した後でもスマラグドゥス(緑玉)を見ることによって、視力を正常な状態に戻すことができる。
パワーストーン的意味の大元発見(笑)
プリニウスの博物誌を丁寧に読んでいくと、現在のパワーストーン的意味につながる記述が見られます。
こうした人間の目で見た”感性”が、脈々と言い伝えられ、そして現在に至る。
すごいことだと思います。
そしてこの表現力。
プリニウスさん自身が石を本当に美しいものと認め、それを語るその作業の中で、たくさんの比喩表現や比較が出てきますが私が好きなフレーズの一つです。
他に、
スマラグドゥス(緑玉)は、離れてみると実際より大きく見える。
それはそれがその色を周りの空気に写すからである。
それは日向でも日陰でもランプの光の中ででも少しも変わらず、いつも穏やかな光を放っている。
そして光を通しやすいので、そのいちばん向こうの端まで透視することができる。
水も同じように、我々を喜ばす性質を持っているが。
” その色を周りに写すから”
いいフレーズです。
そして”水も~”の文章の締め。
本当に心から美しいと思っていることがとても伝わる言葉です。
いきなりふと思い出したかのように話が飛んだり、また、こんな素敵な表現だったり。
読めば読むほど、面白い人だなぁと思います。
ーーー
出典 プリニウスの博物誌(全3巻). (1986). 日本: 雄山閣.
プリニウス(23~79年→古代ローマ時代)が書いた”博物誌”
天文・地文・気象・地理・人種・人類とその発明・動物・植物・農業・造林・金属・絵画と顔料・岩石・宝石など生活に結びついたあらゆる分野を取り扱い、人類初の百科事典と言われます。
この中で、第33巻(金属の性質)・第34巻(銅)・第36巻(石の性質)・第37巻(宝石)が鉱物関連の記述です。
ここに書かれている石の話です。